特に書く事も無いので最近読んだ本でも。
「すべてがFになる」 - 森 博嗣
孤島のハイテク研究所で、少女時代から完全に隔離された生活を送る天才工学博士・真賀田四季。彼女の部屋からウエディング・ドレスをまとい両手両足を切断された死体が現れた。偶然、島を訪れていたN大助教授・犀川創平と女子学生・西之園萌絵が、この不可思議な密室殺人に挑む。
密室殺人モノですが、「犯人がどうやって逃げたか」よりも「犯人がどうやって入ったか」の方にウエイトが置かれたトリックというのは、言われてみれば珍しいですね。「その手があったか!」と思えるか思えないかで評価は分かれると思いますが、あまりに気の長い計画なので、ちょっとどうかとも思います。
その割には逃げ切るのが結構綱渡りだったり、最終的には逃げる気は無いみたいな感じで、トリックありきで、肉付けして話をこしらえました、みたいなのは個人的には好きな部類じゃないです。でも、分厚い割にサッサカと読み進めれたので、読ませる書き方の上手な方なのだと思います。
主要キャラクターには全然感情移入できなかったですけど。
「F」とは何ぞや、という件に関しては、序盤で「7」とか「B」とか「D」とかが出て来たので、その時点で想像は付きましたが、それだけでトリックを見破るのは、さすがに行き過ぎではないのかなと思いました。最終的に「博士は天才だから」で全てを片付けるのも、どうかと思います。
「私が殺した少女」 - 原 寮
まるで拾った宝くじが当たったように不運な一日は、一本の電話ではじまった。私立探偵沢崎の事務所に電話をしてきた依頼人は、面会場所に目白の自宅を指定していた。沢崎はブルーバードを走らせ、依頼人の邸宅へ向かう。だが、そこで彼は、自分が思いもかけぬ誘拐事件に巻き込まれていることを知る。
この話がハードボイルドだとするとちょっと複雑、ミステリーだとすると王道過ぎる、という感じで、ちょうど両者のいいトコ取りでよく出来ていると思いました。管理人の場合、「このミステリーがすごい」に挙げられているため、後者として読んだモノですから、「まさか、あの手の話じゃないよね」と思った通りの結末だった訳なのですが。
ハードボイルドらしく、ひねくれた会話などが面白いのですが、何のネタフリでも無いメインストーリーに全く関係の無い登場人物エピソードを2個も織り交ぜている割には、主人公のキャラクターがイマイチ伝わってこずに、そんな探偵が雁首揃えた警察捜査本部の面々よりも常に先んじて行動出来ているところがちょっと出来過ぎかなぁという気もします。でも、たまにはハードボイルドも面白いモンだなと思いました。
「儚い羊たちの祝宴」 - 米澤 穂信
ミステリの醍醐味と言えば、終盤のどんでん返し。中でも、「最後の一撃」と呼ばれる、ラストで鮮やかに真相を引っ繰り返す技は、短編の華であり至芸でもある。本書は、更にその上をいく、「ラスト一行の衝撃」に徹底的にこだわった連作集。古今東西、短編集は数あれど、収録作すべてがラスト一行で落ちるミステリは本書だけ。
ま、そんな事は無いと思いますが(笑)。この解説を読むと、最後に「どんでん返し」が来るのか、と思ってしまいがちですが、そうではなくて、「あ、なるほど、そいう事ね」という意味の「落ちる」ですね。しかも、本当に「1行」で落ちてるのは『玉野五十鈴の誉れ』だけのように思います。コレだけは本当に最後の1行を書きたいがための話、という感じです。話の行きつく先は予測できても、最後の1行だけはお見事でした。
いずれの話も、ちょっと昔の大金持ちに関わる女の子(娘とか使用人とか)が主人公で、その淡々とした語り口に反して、いや~な事件(?)で人が死んでいく話ばかりで、寒々しくはあるのですが、それぞれの話には何の繋がりも無いのに、全て劇中に同じ名前のサークルが出て来て、最後の話でそのサークルの顛末(でいいのかな?)が書かれるという構成は良く出来ていたと思います。
amazonの書評とか見ていますと「江戸川乱歩を希釈した感じ」みたいな事も書かれていますが、短編なのでそんな事を言っちゃうと何も書けなくなってしまうと思います。今時、本気で全く新しいモノなんて、そうそう創造できないでしょう。それぞれが短いなりに、無駄も無くキッチリ丁寧に書き込まれているという印象です。「インシテミル」はあまり受け付けませんでしたので、管理人的には短編向きな作者なんじゃないかな、と思いました。
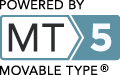
コメントする